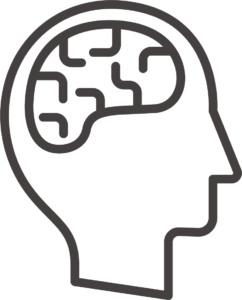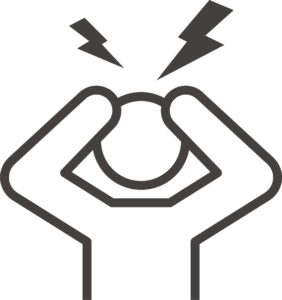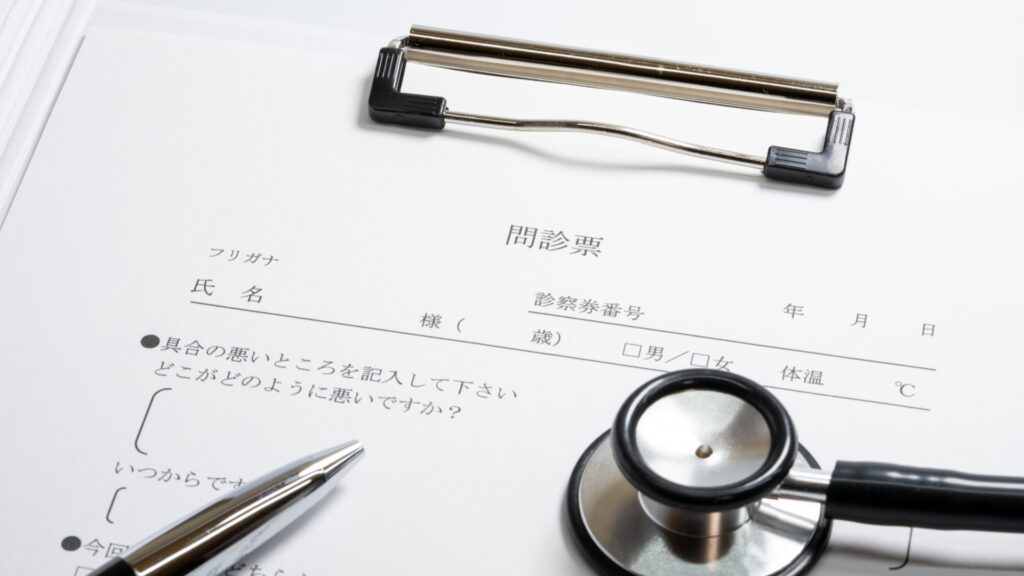
脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)の後遺症に対するリハビリ
脳梗塞や脳出血といった脳血管疾患は、命に関わるだけでなく、手足の麻痺、言葉の障害、感覚の異常、記憶力の低下など、様々な後遺症を残すことがあります。当クリニックでは、これらの後遺症でお困りの方が、日常生活をよりスムーズに送れるよう、専門的なリハビリテーションを通じてサポートしています。
脳のリハビリは、失われた機能を回復させるだけでなく、残された機能を最大限に活用し、生活の質(QOL)を高めることを目的としています。脳の回復は、発症からの期間や後遺症の程度によって個人差がありますが、諦めずに継続することで、少しずつ改善していくことが期待できます。
当クリニックでは、患者様一人ひとりの後遺症の状態や生活目標に合わせて、様々な専門職が連携し、 お一人お一人に沿ったリハビリプログラムを提供します。
1. 理学療法(PT: Physical Therapy)
主に手足の麻痺や体のバランスの障害を改善し、座る、立つ、歩くといった基本的な動作の回復を目指します。
- 関節可動域訓練: 麻痺などで固まりやすい関節の動きを柔らかくします。
- 筋力増強訓練: 弱くなった筋肉を鍛えます。
- バランス訓練: ふらつきを改善し、転倒しにくい体を作ります。
- 歩行訓練: 正しい歩き方を練習し、安定した歩行を目指します。
- 装具の検討・調整: 歩行を補助する装具(例:短下肢装具)の選定や、その使い方の指導を行います。
2. 作業療法(OT: Occupational Therapy)
食事、着替え、入浴、調理など、日常生活に必要な細かな動作(「作業」と呼びます)の回復を目指します。また、記憶力や注意力などの認知機能の改善も図ります。
- 手指の巧緻動作訓練: スプーンを使う、ボタンを留めるなど、細かな手の動きを練習します。
- ADL(日常生活動作)訓練: 食事、更衣、排泄などの練習を通じて、自立した生活をサポートします。
- 高次脳機能訓練: 記憶力、注意力、判断力、問題解決能力などの認知機能の低下に対して、様々な課題やゲームを用いて訓練します。
- 自助具の活用: 必要に応じて、日常生活を楽にするための工夫や、補助具(自助具)の提案を行います。
3. 言語聴覚療法(ST: Speech-Language-Hearing Therapy)
目的: 言葉がうまく出ない(失語症)、ろれつが回らない(構音障害)、飲み込みにくい(嚥下障害)といったコミュニケーションや摂食・嚥下の障害を改善します。
- 構音訓練: 口や舌の動きを練習し、発音を改善します。
- 失語症訓練: 言葉を理解する力、言葉を表現する力を高めるための練習を行います。
- 聴覚訓練: 聞こえにくい場合のサポートや補聴器の調整などを行います。
- 嚥下訓練: 飲み込みやすい姿勢や食べ物の形態を検討したり、飲み込みに必要な筋肉を鍛えたりします。安全に食事ができるようサポートします。
リハビリを進める上で大切なこと
- 継続すること: 脳の回復には時間がかかります。短期間で大きな変化がなくても、地道に続けることが大切です。
- 主体的に取り組むこと: リハビリは、ご自身が積極的に取り組むことで、より効果を発揮します。
- 家庭での実践: クリニックでのリハビリだけでなく、ご自宅でもできる範囲で練習を続けることが重要です。
- ご家族のサポート: ご家族の理解と協力は、リハビリを進める上で大きな力になります。
- 目標設定: 「できるようになりたいこと」を具体的に設定し、それに向かって一緒に取り組んでいきましょう。
当クリニックでは、これらの専門的なリハビリに加え、必要に応じてお薬の調整や、生活上のアドバイスも行います。患者様とご家族の「こうなりたい」という思いに寄り添い、少しでもその目標に近づけるよう、スタッフ一同、全力でサポートさせていただきます。
何かご不明な点や不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご質問ください。
パーキンソン病、認知症などの神経疾患の診断・治療・管理
脳神経内科は、脳、脊髄、神経、筋肉の病気を専門に診る科です。特に、パーキンソン病や認知症といった神経疾患は、時間とともに症状が変化し、日常生活に大きな影響を与えることがあります。当クリニックでは、これらの病気と診断された方が、病気と上手に付き合いながら、できるだけ長く自分らしい生活を送れるよう、きめ細やかな診断、治療、そして継続的な管理をサポートしています。
1. 診断
正確な診断は、適切な治療を行うための第一歩です。
- 詳細な問診:
- いつから、どのような症状が出ているのか(例:手が震える、歩きにくい、物忘れがひどい、言葉が出てこないなど)。
- 症状はどのように変化してきたか。
- ご家族から見た変化(特に認知症の場合、ご本人では気づきにくいことがあります)。
- 既往歴、服用中の薬、生活習慣などを詳しくお伺いします。
- 神経学的診察:
- 手足の動き、筋力、感覚、反射、バランス、目の動き、言葉の能力などを細かく確認します。
- パーキンソン病であれば、特有の震えや体のこわばり、歩行の状態などを評価します。
- 認知症であれば、記憶力や判断力、計算能力などを評価する簡単なテストを行います。
- 画像検査:
- 頭部MRI検査: 脳の萎縮の程度、脳梗塞や脳出血の有無、その他の脳の異常がないかなどを詳しく調べます。
- CT検査: 急な変化や、MRIが撮れない場合に利用することがあります。
- 血液検査・尿検査:
- 体の病気(甲状腺機能異常、ビタミン欠乏など)が原因で、認知症のような症状が出ている場合があるため、それらの除外診断を行います。
- パーキンソン病の場合も、関連する項目を調べることがあります。
- 認知機能検査:
- 長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSE(Mini-Mental State Examination)といった簡易的なものから、より詳細な神経心理学的検査まで、必要に応じて行い、認知機能のどの部分に障害があるのかを評価します。
- その他の検査:
- パーキンソン病では、DATスキャン(ドパミントランスポーターシンチグラフィ)といった特殊な核医学検査を行うこともあります。
- 必要に応じて、脳波検査なども検討します。
これらの検査結果を総合的に判断し、診断を確定します。
2. 治療
神経疾患の治療は、症状を和らげ、病気の進行を穏やかにし、患者様の生活の質を維持・向上させることを目的とします。
- 薬物療法:
- パーキンソン病: ドパミンを補う薬、ドパミンの働きを助ける薬、症状を和らげる薬など、様々な種類があります。患者さんの症状や進行度に合わせて、最適な薬を組み合わせ、細かく調整していきます。
- 認知症: 進行を遅らせる薬(コリンエステラーゼ阻害薬、NMDA受容体拮抗薬など)や、周辺症状(BPSD: 行動・心理症状)を抑える薬(興奮、不眠、幻覚など)を使用します。
- その他の神経疾患についても、それぞれの病気に合わせた薬物療法を行います。
- 非薬物療法:
- リハビリテーション: 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、運動機能の維持・向上、日常生活動作の訓練、認知機能訓練、嚥下訓練、発声訓練などを行います。当クリニックでも、必要に応じてリハビリテーションをご提案し、地域のリハビリ専門施設と連携することもあります。
- 生活習慣の改善: 食事、運動、睡眠、趣味活動など、心身の健康を保つためのアドバイスを行います。
- 環境調整: 認知症の場合、ご自宅の環境を調整することで、転倒予防や自立を促すことができます。
3. 管理とサポート
神経疾患は長く付き合っていく病気が多いため、継続的な管理とサポートが重要です。
- 定期的な診察と評価:
- 症状の変化や薬の効果、副作用の有無を定期的に確認し、薬の量や種類を細かく調整していきます。
- 病気の進行度や生活状況を定期的に評価し、その時点での最適な治療方針を検討します。
- 心理的サポート:
- 病気と診断されたことへの不安や、症状からくるストレスに対して、精神的なサポートも大切です。
- 必要に応じて、専門のカウンセリングや精神科医への連携も検討します。
- 情報提供と相談:
- 病気についての正しい情報提供や、今後の見通しについて丁寧にご説明します。
- 介護保険制度の利用、地域の支援サービス、専門機関の紹介など、生活を支えるための情報提供を行います。
- ご家族からのご相談にも応じ、介護の負担軽減や、病気への理解を深めるお手伝いをします。
- 多職種連携:
- 当クリニックだけでなく、かかりつけ医、地域包括支援センター、ケアマネジャー、訪問看護ステーション、リハビリ専門施設など、様々な専門職と連携し、患者さんを多角的にサポートする体制を整えています。
パーキンソン病や認知症といった神経疾患は、患者様ご本人だけでなく、ご家族の皆様にとっても大きな負担となることがあります。当クリニックは、患者様とご家族が安心して病気と向き合えるよう、寄り添いながら、最適な医療を提供してまいります。
何かご不明な点やご心配なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
頭痛、めまい、しびれなどの症状に対する診療
頭痛、めまい、しびれといった症状は、日常生活でよく経験されるものですが、時には脳や神経の病気が原因となっていることもあります。当クリニックでは、これらの症状でお困りの方が安心してご相談いただけるよう、専門的な知識と経験に基づいて、丁寧な診療を行っています。
これらの症状で「なぜ脳神経内科?」
脳神経内科は、脳、脊髄、末梢神経、筋肉の病気を専門とする診療科です。頭痛、めまい、しびれといった症状は、これらのどこかに異常があることで生じることが多いため、脳神経内科での診察が非常に重要になります。
1. 診察の流れ
まず、症状について詳しくお話を伺います。
- 頭痛の場合: いつから、どのくらいの頻度で、どこが、どのように痛むのか(ズキズキ、ガンガン、締め付けられるなど)、痛みの強さ、持続時間、悪化・軽減する要因(光、音、におい、体を動かすなど)、吐き気や嘔吐、手足のしびれなどの他の症状の有無、市販薬の効果などを詳しくお聞かせください。
- めまいの場合: どんなめまいか(グルグル回る、フワフワする、立ちくらみのような感じなど)、めまいが起きる状況(動いた時、急に立ち上がった時など)、めまいの持続時間、吐き気や耳鳴り、難聴、手足のしびれなどの他の症状の有無などを詳しくお伺いします。
- しびれの場合: どこが、どの範囲でしびれるのか、どんな感覚か(ピリピリ、ジンジン、感覚がないなど)、いつからか、どのくらいの頻度か、力が入らないなどの他の症状の有無、しびれる動作や姿勢などを詳しくお伺いします。
その上で、必要に応じて神経学的診察を行います。
- 手足の動き、筋力、感覚(触覚、痛覚、温覚など)、反射、バランス、目の動きなどを細かく確認し、神経の異常がないかを評価します。
2. 検査
症状や神経学的診察の結果に基づいて、必要と思われる検査を行います。
- 頭部MRI検査: 脳腫瘍、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などの重篤な病気が原因の頭痛や、めまい、しびれの原因となる脳の異常がないかを詳しく調べます。特に、脳の小さな変化も捉えることができるため、非常に有用な検査です。
- 頭部CT検査: 頭部MRI検査が難しい場合や、緊急性が高い場合(出血の確認など)に行うことがあります。
- 血液検査: 炎症や貧血、甲状腺機能異常、糖尿病など、全身の病気が原因で頭痛、めまい、しびれが起きている可能性がないかを調べます。
- 神経伝導速度検査・筋電図検査: しびれの原因が、手足の末梢神経の障害によるものかどうかを詳しく調べます。
- 重心動揺計検査: めまいの原因が体のバランスの異常によるものか、その程度を客観的に評価します。
これらの検査の結果を総合的に判断し、診断を行います。
3. 治療と管理
診断結果に基づき、患者様一人ひとりの症状や病態に合わせた治療法をご提案します。
- 薬物療法:
- 頭痛: 緊張型頭痛や片頭痛など、頭痛の種類によって効果的な薬が異なります。痛みを和らげる薬(急性期治療薬)や、頭痛の頻度や程度を減らすための予防薬を処方します。最近では新しいタイプの片頭痛治療薬も登場しています。
- めまい: めまいの原因(良性発作性頭位めまい症、メニエール病、脳の病気など)に応じた薬を処方します。
- しびれ: 神経の炎症を抑える薬、神経の働きを助ける薬、血流を改善する薬、あるいは神経障害性疼痛に効果のある薬などを処方します。
- 生活指導:
- 頭痛やめまいの誘因となる生活習慣(睡眠不足、ストレス、特定の飲食物など)の改善についてアドバイスします。
- しびれの原因となる姿勢や動作の改善指導を行うことがあります。
- リハビリテーション:
- めまいが続く場合や、平衡機能の改善が必要な場合には、平衡訓練などリハビリテーションをご提案することもあります。
- しびれで運動機能に影響が出ている場合も、リハビリテーションが有効な場合があります。
- 専門機関との連携:
- より専門的な治療や検査が必要な場合(例えば、脳腫瘍の手術など)には、連携する高次医療機関へご紹介します。
頭痛、めまい、しびれといった症状は、つらいだけでなく、不安を感じることも多いと思います。当クリニックでは、患者様の話を丁寧に聞き、適切な検査と診断を行い、病気に対する不安を解消しながら、症状の改善に向けて一緒に取り組んでまいります。
もし、これらの症状でお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。