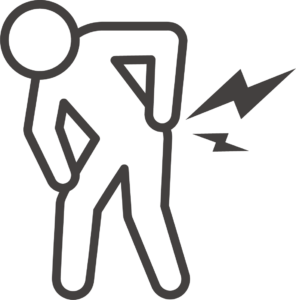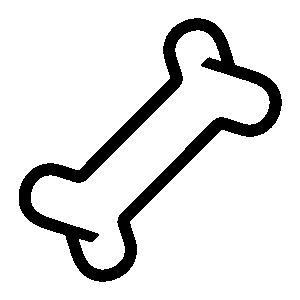けが(骨折、捻挫、打撲など)の治療
整形外科では、骨折、捻挫、打撲といった様々な怪我に対して、患者様一人ひとりの状態に合わせた治療を行っています。
まず、どのような怪我をされたのか、詳しくお話を伺います。いつ、どこで、どのようにして怪我をされたのか、痛む場所や程度、動かせるかどうかなど、できるだけ詳しく教えてください。
その上で、必要に応じて検査を行います。
- レントゲン検査: 骨折の有無や骨の状態を確認するための基本的な検査です。
- CT検査: より詳しく骨の状態や関節のずれなどを確認したい場合に、特殊なレントゲン撮影を行います。
- MRI検査: 靭帯や軟骨、神経などの状態を詳しく調べたい場合に、磁気を使った検査を行います。
- 超音波検査: 筋肉や靭帯の状態を観察したり、関節の中に水が溜まっていないかなどを確認したりするのに用います。
これらの検査の結果をもとに、治療方針を決定します。治療法は、怪我の種類や程度、患者さんの年齢や活動レベルなどによって異なりますが、大きく分けて以下のようなものがあります。
※CT検査、MRI検査は当院にはございませんので、他の医療施設をご紹介いたします。
1. 保存療法
手術を行わずに、自然治癒力を高めたり、症状を和らげたりする治療法です。
- 安静: 怪我をした部分を動かさないようにすることで、組織の修復を促します。
- 固定: ギプス、シーネ、サポーターなどを用いて、患部を固定し、安定させます。これにより、痛みを軽減し、骨や靭帯のずれを防ぎます。
- 冷却: 怪我をしてすぐに行うことで、炎症や腫れを抑える効果があります。
- 圧迫: 包帯などで患部を圧迫することで、腫れを抑えます。
- 挙上: 患部を心臓より高い位置に保つことで、腫れの軽減を促します。
- 薬物療法: 痛み止め(内服薬や湿布など)や、炎症を抑える薬などを使用します。
- リハビリテーション: 痛みが和らいできたら、関節の動きを取り戻したり、筋力を回復させたりするための運動療法を行います。理学療法士などの専門家が、患者様の状態に合わせてメニューを作成し、指導します。
2. 手術療法
保存療法では十分な効果が得られない場合や、骨折のずれが大きい場合、靭帯が完全に切れてしまった場合などに行われます。
※当院では手術を行えないため、大きな病院をご紹介いたします。
- 骨折の手術: 折れた骨を元の位置に戻し、金属製のプレートやネジ、ワイヤーなどで固定します。
- 靭帯や腱の手術: 切れた靭帯や腱を縫い合わせたり、他の組織で再建したりします。
- 関節の手術: 関節のずれを整えたり、損傷した軟骨などを修復したりします。
手術の方法も、患者様の状態や怪我の種類によって様々です。手術が必要な場合は、医師から手術の内容、方法、リスク、術後のリハビリテーションなどについて詳しく説明がありますので、ご安心ください。
治療の期間は、怪我の種類や程度によって大きく異なります。骨折の場合、骨が完全にくっつくまでには数週間から数ヶ月かかることもあります。捻挫や打撲の場合でも、痛みが完全に引くまでには時間がかかることがあります。
治療中は、医師や理学療法士などの指示を守り、無理のない範囲でリハビリテーションに取り組むことが大切です。もし、治療中に何か不安なことや疑問なことがあれば、遠慮せずに医師や看護師にご相談ください。
一日も早く、元の生活に戻れるよう、私たちも精一杯サポートさせていただきます。
関節の痛み、腰痛、神経痛などの治療
関節の痛み、腰痛、神経痛といった慢性的な痛みは、日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的にもつらいものです。整形外科では、これらの痛みの原因を特定し、患者様一人ひとりに合わせた治療法をご提案しています。
まず、どのような痛みでお悩みなのか、詳しくお話を伺います。いつから、どこが、どのように痛むのか、痛む時間帯やきっかけ、日常生活での困りごとなど、できるだけ詳しく教えてください。
その上で、必要に応じて検査を行います。
- レントゲン検査: 関節の変形や骨の状態、腰椎のずれなどを確認します。
- MRI検査: 椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、靭帯や神経の状態などを詳しく調べます。
- CT検査: より詳しく骨の状態を確認したい場合に、特殊なレントゲン撮影を行います。
- 神経伝導速度検査・筋電図検査: 末梢神経の障害の有無や程度を調べます。
- 血液検査: 関節リウマチなどの炎症性疾患が隠れていないかを確認します。
これらの検査の結果をもとに、治療方針を決定します。治療法は、痛みの原因や程度、患者さんの年齢や活動レベルなどによって異なりますが、大きく分けて以下のようなものがあります。
※CT検査、MRI検査、神経伝導速度検査・筋電図検査は当院にはございませんので、他の医療施設をご紹介いたします。
1. 保存療法
手術を行わずに、痛みを和らげ、日常生活を送りやすくするための治療法です。多くの場合、まずは保存療法から開始します。
- 薬物療法:
- 痛み止め(内服薬、外用薬): 炎症を抑えたり、痛みを和らげたりします。
- 筋弛緩薬: 筋肉の緊張を和らげ、痛みを軽減します。
- 神経障害性疼痛治療薬: 神経の痛みに効果を発揮します。
- 関節内注射(ヒアルロン酸、ステロイド): 関節の痛みを直接抑えます。
- 装具療法: コルセットやサポーターなどを用いて、関節や腰を安定させ、負担を軽減します。
- 理学療法・運動療法(リハビリテーション):
- 温熱療法: 温めることで血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。
- 牽引療法: 首や腰を引っ張ることで、神経への圧迫を軽減します。
- 運動療法: 関節の可動域を広げたり、痛みを支えるための筋力を強化したりします。理学療法士などの専門家が、患者さんの状態に合わせてメニューを作成し、指導します。
- 神経ブロック療法: 痛みの原因となっている神経に局所麻酔薬などを注射し、痛みを遮断します。
2. 手術療法
保存療法では十分な効果が得られない場合や、日常生活に著しい支障がある場合、神経の圧迫が強い場合などに行われます。
※当院では手術を行えないため、大きな病院をご紹介いたします。
- 椎間板ヘルニア手術: 飛び出した椎間板を取り除くことで、神経の圧迫を解除します。
- 脊柱管狭窄症手術: 狭くなった脊柱管を広げ、神経の圧迫を解除します。
- 関節変形症手術(人工関節置換術など): 傷んだ関節を人工の関節に置き換えることで、痛みを軽減し、動きを改善します。
- 脊椎固定術: 不安定な脊椎を金属などで固定し、痛みを軽減します。
手術の方法も、患者様の状態や痛みの原因によって様々です。手術が必要な場合は、医師から手術の内容、方法、リスク、術後のリハビリテーションなどについて詳しく説明がありますので、ご安心ください。
慢性的な痛みの場合、治療には時間がかかることもあります。大切なのは、医師や理学療法士などと協力しながら、根気強く治療に取り組むことです。日常生活での注意点や、ご自身でできる運動療法などもお伝えしますので、ぜひ実践してみてください。
もし、治療中に何か不安なことや疑問なことがあれば、遠慮せずに医師や看護師にご相談ください。少しでも痛みが和らぎ、快適な生活を送れるよう、私たちも精一杯サポートさせていただきます。
骨粗鬆症の診断・治療・予防
骨粗鬆症は、骨がスカスカになって弱くなり、骨折しやすくなる病気です。特に、気がつかないうちに進行することが多いため、「静かなる病気(silent disease)」とも呼ばれています。しかし、適切な診断と治療、そして予防を行うことで、骨折のリスクを減らし、健康な生活を送ることができます。
1. 骨粗鬆症の診断
骨粗鬆症の診断は、主に以下の検査に基づいて行われます。
- 骨密度測定: 専用の機械を使って、骨の密度を測定します。これが最も重要な検査で、骨の強度を直接評価することができます。当院では、DXA(デキサ)法という精度の高い方法で測定を行います。
- レントゲン検査: 骨折の有無や、骨の変形の状態を確認します。ただし、初期の骨粗鬆症ではレントゲンで異常が見つからないこともあります。
- 血液検査・尿検査: 骨の新陳代謝に関わるホルモンやミネラルの状態、骨吸収(骨が溶けること)の程度などを調べます。これにより、骨粗鬆症の原因や進行の程度を把握するのに役立ちます。
- 問診: 患者様の既往歴、生活習慣、家族歴などを詳しくお伺いします。骨粗鬆症のリスク因子(閉経、加齢、喫煙、飲酒、運動不足、特定の病気や薬の使用など)を確認します。
これらの検査結果を総合的に判断して、骨粗鬆症の診断を行います。
2. 骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の治療の目的は、骨折のリスクを減らし、骨の強度を高めることです。治療法には、主に以下のものがあります。
- 薬物療法: 骨密度を高めたり、骨の吸収を抑えたりする様々な種類の薬があります。
- 骨吸収抑制薬: 骨が溶けるのを防ぐ薬(ビスホスホネート製剤、SERM、抗RANKL抗体など)
- 骨形成促進薬: 骨を作るのを助ける薬(副甲状腺ホルモン製剤、スクレロスチン阻害薬など)
- 活性型ビタミンD製剤: カルシウムの吸収を助け、骨の形成を促進します。
- ビタミンK2製剤: 骨の形成を助けるとともに、骨質の改善にも役立ちます。 患者さんの骨の状態や全身の状態に合わせて、最適な薬を選択し、内服薬や注射薬などで治療を行います。
- 食事療法: バランスの取れた食事を心がけ、特にカルシウムとビタミンDを十分に摂取することが重要です。
- カルシウム: 乳製品、小魚、緑黄色野菜などに多く含まれています。
- ビタミンD: 魚介類、きのこ類などに含まれており、日光浴によっても体内で作られます。 必要に応じて、カルシウムやビタミンDのサプリメントを医師の指示のもとで使用することもあります。
- 運動療法: 適度な運動は、骨に刺激を与え、骨密度の維持や向上に役立ちます。
- ウォーキングや軽いジョギングなどの体重負荷運動: 骨に適切な刺激を与えます。
- 筋力トレーニング: 骨を支える筋肉を鍛え、バランス感覚を養い、転倒予防につながります。 患者様の体力や状態に合わせて、無理のない範囲で継続することが大切です。
- 生活習慣の改善:
- 禁煙: 喫煙は骨密度を低下させるため、禁煙が重要です。
- 過度な飲酒を控える: 過度の飲酒も骨に悪影響を及ぼします。
- 転倒予防: バランス感覚を養う運動や、住環境の整備(滑りやすい場所の改善、手すりの設置など)が大切です。
3. 骨粗鬆症の予防
骨粗鬆症は、早期から予防に取り組むことが非常に重要です。
- 若い頃からの骨貯金: 成長期にしっかりと骨を育てておくことが、将来の骨粗鬆症予防につながります。バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。
- 閉経後の対策: 女性は閉経後に骨密度が急激に低下することがあります。ホルモン補充療法(HRT)などの選択肢もありますので、医師にご相談ください。
- 定期的な骨密度検査: 特に骨粗鬆症のリスクが高い方は、定期的に骨密度検査を受け、骨の状態を把握することが大切です。
- 食事・運動習慣の維持: 成人になってからも、カルシウムやビタミンDを意識した食事、適度な運動を継続することが重要です。
- 転倒予防: 日頃からバランス感覚を養う運動を取り入れ、転倒しにくい生活環境を整えましょう。
骨粗鬆症の治療と予防は、患者さんご自身が主体的に取り組むことが大切です。当院では、患者様一人ひとりの状態やライフスタイルに合わせた治療計画をご提案し、食事や運動のアドバイスも行っています。
もし、骨粗鬆症について心配なことや疑問なことがあれば、遠慮せずにご相談ください。一緒に骨の健康を守り、いきいきとした生活を送れるようサポートさせていただきます。
スポーツによるケガや障害の治療、スポーツ復帰支援
スポーツは、健康維持や体力向上に役立つ素晴らしいものですが、時には怪我や障害を引き起こすことがあります。整形外科では、スポーツを愛する皆さんが、安全に、そして再び思い切りスポーツを楽しめるよう、専門的な知識と技術でサポートしています。
まず、どのようなスポーツで、どのような怪我や障害にお悩みなのか、詳しくお話を伺います。受傷時の状況、痛む場所や程度、どのような動作で痛みが出るか、これまでの治療歴などを詳しく教えてください。
その上で、怪我の状態を正確に把握するために、必要に応じて検査を行います。
- レントゲン検査: 骨折や脱臼、骨の変形などを確認します。
- MRI検査: 靭帯、腱、軟骨、筋肉などの軟部組織の損傷や炎症、神経の圧迫などを詳しく調べます。
- CT検査: 細かい骨折や関節の状態をより詳しく確認したい場合に用います。
- 超音波検査: 筋肉や靭帯の状態をリアルタイムに観察したり、関節の動きを確認したりするのに役立ちます。
- 関節鏡検査: 関節の中に小さなカメラを入れて、内部の状態を直接観察し、必要に応じて治療を行うこともあります。
これらの検査の結果をもとに、治療方針を決定します。治療は、怪我の種類や程度、競技の種類やレベル、復帰への希望時期などを考慮して、患者さんと一緒に最適な方法を選択していきます。
1. 急性期の治療(怪我をしてすぐの時期)
炎症や痛みを抑え、組織の回復を促すことが重要です。
- RICE処置:
- Rest(安静): 怪我をした部分を動かさないようにします。
- Ice(冷却): 炎症や腫れ、痛みを抑えるために冷やします。
- Compression(圧迫): 腫れを防ぐために包帯などで適切に圧迫します。
- Elevation(挙上): 患部を心臓より高い位置に保ち、腫れを軽減します。
- 薬物療法: 痛み止めや炎症を抑える薬(内服薬や外用薬)を使用します。
- 装具療法: サポーターや固定具などを用いて、患部を保護し、安静を保ちます。
2. 回復期・リハビリテーション
痛みが和らいできたら、スポーツ復帰に向けて段階的にリハビリテーションを開始します。専門の理学療法士などが、患者様の状態に合わせて個別のプログラムを作成し、指導を行います。
- 痛みのコントロール: 運動療法や物理療法(温熱療法、電気刺激療法など)を用いて、残存する痛みを軽減します。
- 関節可動域の改善: 硬くなった関節の動きを正常に戻すためのストレッチや関節モビライゼーションを行います。
- 筋力強化: 損傷した部位だけでなく、全身の筋力をバランス良く鍛え、再発予防につなげます。
- バランス・協調性の改善: スポーツに必要なバランス能力や、全身のスムーズな動きを取り戻すためのトレーニングを行います。
- 持久力の回復: 必要に応じて、心肺機能を高めるトレーニングを行います。
- フォームの修正・動作指導: 怪我の原因となった可能性のある 不自然な フォームや動作を修正し、効率の良い動きを習得します。
3. スポーツ復帰支援
リハビリテーションの最終段階では、徐々にスポーツ特有の動作を取り入れていきます。
- 段階的な負荷の増加: 軽い運動から始め、徐々に強度や時間を上げていきます。
- 競技特性に合わせた練習: 実際に競技で行う動作に近い練習を行い、感覚を取り戻します。
- メディカルチェック: スポーツ復帰前に、医師や理学療法士が再度評価を行い、安全に復帰できる状態であるかを確認します。
- 再発予防のための指導: 今後のトレーニング方法や、注意すべき点などを具体的に指導します。
整形外科医、理学療法士、トレーナーなどが連携し、それぞれの専門性を活かして、患者様のスポーツ復帰を全力でサポートします。私たちは、ただ怪我を治すだけでなく、「なぜ怪我をしてしまったのか」という原因を探り、再発予防まで含めたトータルなサポートを目指しています。
スポーツ復帰への道のりは、決して 簡単ではありませんが、私たちと一緒に一歩ずつ進んでいきましょう。不安なことや疑問なことがあれば、いつでも遠慮せずにご相談ください。再び、最高のパフォーマンスを発揮できるよう、精一杯サポートさせていただきます。